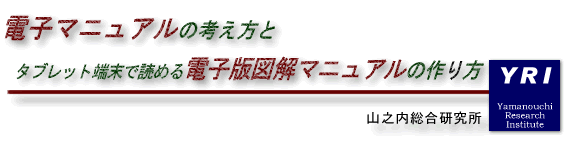
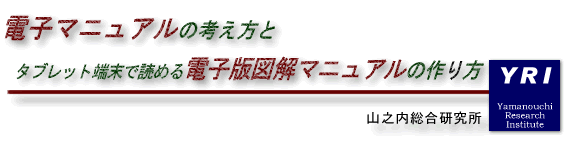
|
ここからの数セクションでは、文書スタイルを基盤としかつタブレット端末の狭い画面で“読める”電子版図解マニュアルの考え方・作り方を概説します。
電子書籍端末(あるいは電子文書閲覧端末)としてのタブレット端末の登場には、印刷物ではなしえない「文書の新たな可能性」が開けたとともに「紙に記された文書を“読む”」が「PCの操作によってPCの画面で読む」を経て「書籍に近い大きさ・重さの端末を書籍と同様な位置関係・扱い方で“読む”」に回帰した一面があります。この事実は、印刷文書から電子文書へ媒体は変わっても、「人にとって読みやすい文書形態」の本質は変わらない証とも言えます。 |
電子文書は、「PCで読む」から「携帯性が高いタブレット端末(あるいは電子書籍端末)で読む」によってさらに利便性が高まります。ただし、一般的なノートPC(例:13インチ)よりも画面サイズが制限されることを念頭に置かなければなりません。また、印刷文書のA4判見開きと比べると、1/4程度の表示領域にすぎません。
仮にタブレット端末で代表的な「4:3の縦横比(アスペクト比)を有する10インチ程度の画面(1024×768ピクセル)」は、用紙規格のA5判(148×210mm)に近い大きさです。
「画面が狭い」は、執筆者にとっては「表現に制約を受ける」、読者にとっては「全体を見通しづらい」に通じます。
マニュアルを含め実務文書では、「読んでいる箇所(部分)が当該のセクション(全体)の中でどのような位置付けにあるいのか」あるいは「部分と部分がどのような関係にあるのか」が重要です。 この点で印刷文書は2ページの見開きで全体を見通せ、いくつかの箇所を比較あるいは行きつ戻りつして読めます。電子マニュアルでも、見開きの利便性までは求めなくとも画面の狭さを補う工夫が必要です。
比較的に小さな判型で出版される小説は、部分に着目して読みます。全体は読者の「イメージ」として少しずつ構築されて行きます。また、新聞の記事もマニュアルの1セクションに比べ長くはありません。また、記事それぞれが独立性を有しています。大きく開いて見出しを見渡し、折りたたんで部分を読む習慣もあります。

タブレット端末で読める電子マニュアルを作成するには、 「文書作成の基本(見出し構成、ページの書式)」に立ち返るとともに「電子媒体ならではの機能」によって狭い画面での読みやすさと扱いやすさを実現する必要があります。
「電子文書は“ワンソース・マルチユース(one source multi-use:一つのファイルで表示域・縦横が自由)”のはず」とのご意見があると思います。しかし、「自由度が高い」は「どちらつかず」にもなります。実務文書では、ことさらに自由度を求めるよりも利用者が電子マニュアルを使う状況(7インチから11インチ程度の画面)を想定し、画面に応じた使い勝手のよいページレイアウトと書式を選ぶのが適切と言えます。
タブレット端末の狭い画面で「基本事項(操作の指示)」と「付帯的重要事項(操作の必要性・有効性あるいは条件など)」を関係付けて表すには、「図解マニュアル」とするのが適切です。
ただし、「文(読む)を極力排して、図(見る)を主体にする」のが図解ではありません。「図中に要点(読む)を示す」とともに「段落を統一された書式によって視覚的・構造的に表す」のが本来の図解です。

図解の文書では、セクションを構成する段落を書式によって要素化(段落全体をセクションを構成する要素と扱うとともに段落を構成する文も要素化)します。単に段落を連ねるのではなく、それぞれの位置付けに応じた書式(文字の大きさ、字下げなど)で表します。段落の要素化により、タブレット端末の画面であっても読者は“見ただけで”それぞれの位置付けを見分けられます。
マニュアルならば、指示文とその補足で文字の大きさと書体を変えるのが一般的です。また、注記にはそれとわかる注意喚起シンボルを用います。電子マニュアルならばこれに色使いが加わります。また、手順番号を強調して指示文に視線を誘導します。
図解マニュアルでは、ページ末を調整するのが原則です。「段落の途中でページ末となり次のページに続く(例:指示文と注意が別のページになる)」あるいは「段落とこれに対応すべき図が次のページに送られる」ことはありません。
ページ末が調整されることによって、利用者は「区切り」を付けて次のページに進めます。タブレット端末の狭い画面で段落の続きを読もうとすると、利用者の理解に負担がかかります。
図解化による読むと見るの相互補完は、「読むに伴う負担の一部を見るに分散」とも言えます。執筆者にとっては、「文(あるいは図・表)だけで表そうとすると過大になりうる負担の一部を図・表(あるいは文)への振り分け」にもなります。
電子マニュアルにおいても、「主体的に読者が読む部分」と「補足的(あるいは受動的)に見る部分」を組み合わせることがポイントです。
実践テクニカルライティングセミナー
マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント
Copyright: Takaaki-YAMANOUCHI/1995-2019
山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所
Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute, Ltd.