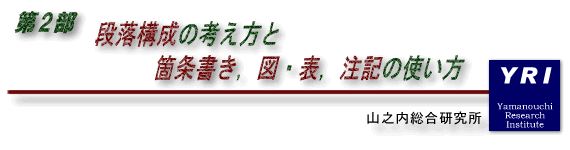
![]()
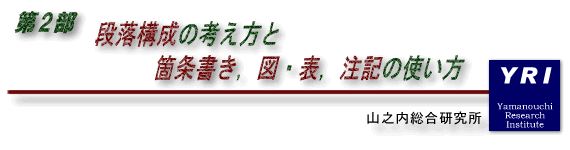
|
ここでの「注記」とは、注見出しが付いた補足文です。また、「副本文」とは注見出しの代わりに段落記号(*など)が付いた補足文です。いずれも補足文の主従関係を書式によって表す手法です。 |
「主文を直接に補足しない付帯的な補足文」の位置付けを“より明確”にするために「注記」あるいは「副本文」を使います。補足文として段落内に組み入れると「段落が長くなる」あるいは「位置付けが埋もれてしまう」場合に有効です。
付帯的な重要事項あるいは参照先などがその対象となります。
また、補足文が長いもしくは補足文が数文続くため主文の位置付けが曖昧になりがちな場合に、補足文の一部を注記もしくは副本文にすると効果的です。
長い段落は、読者にも執筆者にも負担です。注記および副本文によって「大局的には一つの段落」だが、見た目にも主従関係がある「主段落」と「注記(もしくは副本文)」の構成にすると、主文、補足文のいずれも位置付けが明確になります。
読みやすいとされる段落は150字程度(A4版・縦使い・横書き・10ポイントに換算して3.5行程度)です。横道にそれますが、Twitterは140字以内の「つぶやき」です。また、江戸時代の離縁状の俗称は「三行半(みくだりはん)」です(ただし、字数は読み下しでも90字程度)。
「伝えようとする事項の言語化」と「受け手の認知力」との兼ね合いから定着した目安が150字と言えます。技術文書では、長い用語が多用されるため2割増しの180字あるいは200字程度を目安にしてもよいと考えます。

当然ながら、注記および副本文はいずれも「補足」の位置付けです。段落の直後に置き、段落を上回らない行数で表すのが適切です。段落を伴わず、注記あるいは副本文が単独で存在しては不自然です。
5行もしくはそれ以上にわたる注記および副本文は補足の範囲を超えるため、段落との主従関係が崩れてしまいます。
1段落に相当する「長い補足」は、補足ではなく見出し構成の一部として扱うのが適当です。分量がありかつ読者の目に止めるべき事項を補足扱いにすると、重要な事項が目次に採録されず読者に見落とされる可能性があります。
余談ですが、当サイトの解説ではこの「副本文」を多用しています。HTML文書は印刷文書と比べ表示の精細度が低く、3行以上の段落は読みづらく感じられます。当サイトでは補足文の一部を積極的に副本文で表す手法を用いてます。
当サイトの主旨(プレビュー版)により、解説の一部を省略しています。見直し方と見直し例は、出張開催セミナーで解説します。

実践テクニカルライティングセミナー
マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント
Copyright: Takaaki-YAMANOUCHI/1995-2020
山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所
Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute, Ltd.