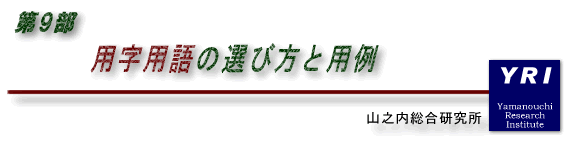
![]()
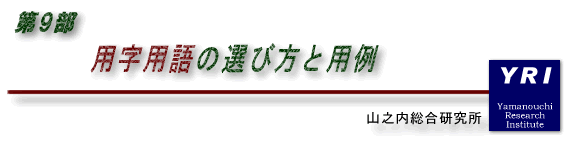
|
技術文書では、さまざまな分野の用語を複合的に扱う場合があります。この場合は「文書テーマの分野の原則を基本とし、他の分野の用語(当該分野で発生した用語)を用いる場合には例外扱いとして当該分野の表記に従う」という考え方が一般的です。 |
同じ外来語のカタカナ表記でも専門分野による違いがあります。機械工学の分野では“energy”を「エネルギ」と表記しますが、物理の分野では「エネルギー」と長音記号を付けるのが一般的です。
もちろん意味するところは同じです。これらは各分野の学会が中心になって作成する文部科学省学術用語集による違いに由来します。
「外来語の表記」(平成3年 内閣告示第二号)では“語形やその書き表し方については慣用が定まっているものはそれによる”、“分野によって異なる慣用が定まっている場合には、それぞれの慣用によって差し支えない”としています。
同じ外来語のカタカナ表記が、専門用語として使われる場合と一般用語として使われる場合で異なる例があります。要は、原則なり裏付けのある慣用に従がいつつ、読者の理解のしやすさ(違和感がないこと)を考慮し、統一して使うことです。すべてに対応できる原則を作ろうとすると無理が生じます。
本来ならば前者の「インタフェース」が技術文書では適切なカタカナ表記ですが、よく目にするのは後者「インターフェイス」です。慣用的な表記が一般用語化した例といえます。このような場合には、ごく専門的な文書(たとえば特定ユーザ対象のマニュアル)以外は後者の一般表記を使用しても差し支えないと思います。
「外来語の表記」(平成3年 内閣告示第二号)が告示される以前から電子・情報通信分野の用語集では「インタフェース」と表記されています。
もちろん、「interface」は電子・情報通信分野に限った用語ではありません。しかし、今日使われている「interface」は主に電子・情報通信分野の語が起源といえます。
本例の場合には、それぞれ原音に沿った表記を認めそのまま使うのが自然と考えます。あえて「インターラクティブ」にする必要もないと思います。
どちらも同じ文書に使いそうな用語です。しかし、一般用語の視点から考えると前者になじみのある読者は少なく、後者は圧倒的に一般語化しています。
一般読者が対象の文書ならば「デジタルハイビジョン対応ディスプレイ」と表記しても違和感がないと思います。
専門用語のより所である日本工業規格(JIS)では「ディジタル」としています。しかし、一般用語としては「デジタル」が定着しました。同様に「ディスプレイ」もすでに一般用語と言えます。
実践テクニカルライティングセミナー
マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント
Copyright: Takaaki-YAMANOUCHI/1995-2020
山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所
Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute, Ltd.