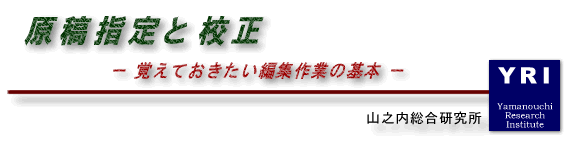
![]()
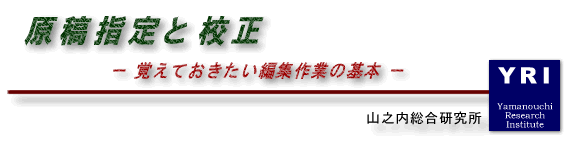
製作担当者から校正刷が届いたら必ずすることがあります。一つは、校正刷の日付と校数の確認です。校正刷の最初に、「初校、2001/5/30」のように「第何校であるか」と「いつ作成されたものか」がわかるようにはっきり明記しておきます。
DTPが主体の今日ではプリンタ出力された校正刷がよく使われます。しかし、そのままでは校正刷の日付と校数が不明ですので、最初のページに少し太めのペン(赤あるいは青)で明記するのが一般的な方法です。
DTPソフトには校正の片隅に日付・時間を自動的にプリントする機能があります。しかし、これらはきわめて小さいうえに本文と同じ色で印刷されるため見落としがちです。意識してバージョンを管理する意味でもあらためて手書きで記入することを勧めます。
しばしば校数を「Ver.2」などのようにバージョン番号形式にすることがあります。しかし、バージョン番号形式は発行後の「版数管理」に使うことがあるためこれと混同しやくすなります。校正では「初校」、「再校」、「3校」・・・とするか「第1校」、「第2校」、「第3校」、・・・とするようにしてください。さらに、「Ver2.5」などと中間バージョンを付ける例をみかけることもありますが、これも意味が曖昧です。
また、製作担当者から控用を含めて2通あるいは3通の校正刷(コピー)が届くことがあります。この際には必ず1通を正(オリジナル)として、上記の日付・校数と同様に「正」と明記してください。残りのコピーには、「副」(複数ならば「副1」、「副2」・・・)と明記します。
以降、製作担当者と校正のやりとりをする場合は必ずこの「正」をもって行うようにしてください。修正などはすべて「正」に集約し、修正が複数の校正刷に分散するようなことは絶対にしないでください。
先に述べた日付・校数の明記もこの正・副の明記も本来は製作担当者がすべきことだと思います。しかし、これをする製作担当者はいつのまにか少なくなりました(ほとんどなくなったといってもよいでしょう)。少なくとも日付・校数ンの明記くらいは製作担当者の管理上すべきではないかと思います。
製作担当者には必ず赤字の入った「正」校正刷を渡してください。なお、渡す前には手元控え用として「正」校正刷のコピーをとり、「正(控)」と明記しておくとよいでしょう。
赤字入れ(あるいは赤字合わせ)が終わると、これを製作担当者に渡して修正作業をしてもらうことになります。しかし、しばしばこの後で修正事項を見つける場合があります。この場合には追加修正の内容によって二通りの対応があります。
一つの修正が数ページにわたる修正(内容の入れ替え、削除など)の場合には緊急の対応をする必要があります。手元控え用の「正(控)」に明確に赤字で記入してその部分を製作担当者に渡して伝えます。
この追加赤字の入った「正(控)」もコピーをとり、手元控えにとじこんでおきます。この際、後から追加して修正であることがわかるように付箋でマーキングをして次の校正で念入りに確認します。
製作担当者がすでに修正作業を始めているのに小さな修正(文字修正など)を指示することはかえって混乱をきたし作業効率が悪くなります。このような場合には手元控え用の「正(控)」に明確に赤字で記入して次の校正の際にその修正を記入します。
この後から追加した修正を忘れないようにしなければなりません。付箋でマーキングをして次の校正で忘れず記入します。
どの程度の修正にどちらの方法をとるかはケース・バイ・ケースといえます。事前に製作担当者と打ち合わせておく必要がよいでしょう。
![]()
テクニカルライティングセミナー
マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント
Copyright:Takaaki-YAMANOUCHI/2002-2010
山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所
Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute,Ltd.
![]() takaaki@yamanouchi-yri.com
takaaki@yamanouchi-yri.com