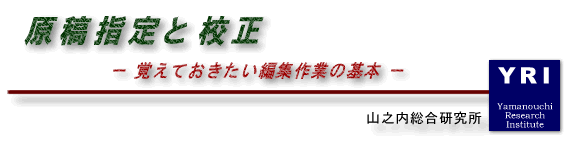
![]()
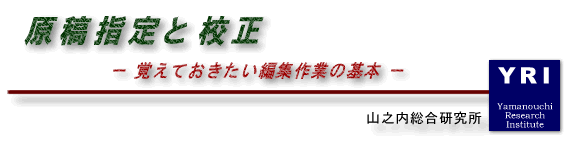
このコーナーの最初で、原稿の執筆が終わっただけでは完成原稿とはいえないと述べました。「原稿調整」とは、原稿の執筆が終わった後に、原稿を執筆者の視点と読者の視点で読み直してチェックすることです。原稿に具体的に赤字をいれ、ワープロなどで修正します。
この「原稿調整」をきちんとしておくかどうかで後の工程が大きく変わってきます。原稿調整をしておかなかったばかりに後の校正の段階になって大幅な修正が入り、完成が期日に間に合わないという例をよく見かけます。
しばしば、「急ぐから原稿を見直している時間はない。問題があれば校正のときに修正すればよい。むしろ校正のほうが直しやすい」と主張する人がいますが。これにはまったく同意できません。校正の際に修正するというのは問題の先送りです。急ぐからこそ原稿の完成度を高めて後の工程がスムーズに進むようにすべきです。
また、「校正のほうが直しがしやすい」というのももってのほかです。校正は出版物としての完成度を上げる工程であり、原稿を完成させる工程ではありません。
「原稿調整」は文書作成のまとめに慣れたコーディネータ(あるいは執筆者の代表者)が一括して行うのがよいでしょう。あまり時間をとる必要はありません、以下に示すような原稿段階ですべき点をチェックしておけばよいのです。
筆者が「原稿調整」について説明すると「校閲のことですか」という質問をされる人がいます。確かに「誤りや不備を正す」という意味では“校閲”と共通しています。しかし、“校閲”には高い見識の人が査読するという意味合いがあるように思われます。
ここでいう「原稿調整」には、“原稿を企画して執筆した執筆者の視点と読者の視点で読み返して原稿の完成度を上げる”意味があることを理解していただくために“校閲”とはあえて区別をしたいと思います。
原稿調整でチェックすべき事項は以下の表に示すような点です。
まずは、目次や執筆要領と照らして「当初目指した内容になっているか」という視点で読み直してください。次に「不統一やもれがないか」あるいは「内容上の誤り、不適切な表現はないか」など、執筆者の立場でチェックしてください。
この際、しばしば内容に無理や矛盾した点を見つけることがあります。たとえば、「同じ用語を複数の意味に用いている」などです。これは複数の担当者で分担執筆した場合によくあります。このような問題点を見つけ出すためにも原稿調整は重要です。
もう一つのポイントは、読者の立場で読み直すことです。製品の開発者であることをいったん忘れて、「その製品についてはよく知らない」という読者(ユーザ)の立場で最初から読み直したり、あるいは「このような場合にはどのような使い方をすればよいのか」というユーザの気持ちになってチェックしてみることです。
読者の視点になることが難しいと思われるかもしれませんが、ご自身が他の製品マニュアルや解説書を読んだ際に感じた良い点、悪い点を思いだしてみてください。「読者指向になるためのポイント」や「わかりすさ」のポイント」は当ホームページでいくつか述べていますので参考にしてみてください。
チェックの視点 | チェックポイント |
企画・目次に照らしたチェック | 説明不足、もれ・重複の有無、ページ数の不足・過多、図・表の不足・過多 |
執筆要領に照らしたチェック | 用語・文体の統一(とくに分担執筆の際の不統一) |
記述の正確さ、読みやすさのチェック | 図・表も含めた内容のわかりやすさ |
![]()
テクニカルライティングセミナー
マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント
Copyright:Takaaki-YAMANOUCHI/2002-2010
山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所
Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute,Ltd.
![]() takaaki@yamanouchi-yri.com
takaaki@yamanouchi-yri.com