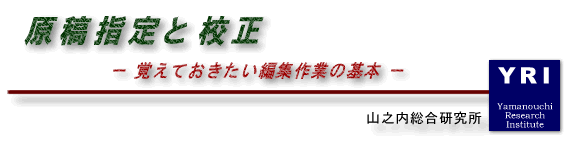
![]()
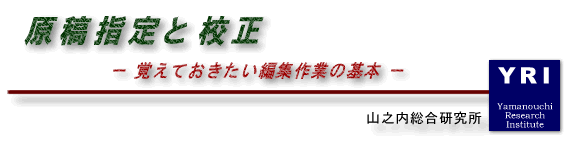
再校校正とは、赤字が入った「初校」とこれを修正した「再校」とを照らし合わせて、初校が正しく修正されているかを確認する作業です。修正した再校と赤字が入った照合するためこれを「赤字合わせ」ともよぶことがあります。
この「赤字合わせ」に加えて、再校校正でもう一つしなければならない作業があります。再校を注意深く読み、最終的に誤りが残っていないかを確認する「素読み」です。
原稿作成の段階で十分に読みやすさや正確さに配慮するのが基本です。ここでは出版物製作の最終段階として重大な誤りがないか念を入れて確認するために素読みをします。
もちろん、最終段階ですから、大幅な内容の追加などは避けなければなりません。数値や名称の誤りなど読者に大きな影響を与えかねない誤りがないかどうかに慎重に確認しておく必要があります。
再校校正では、まず「赤字合わせ」をして、それから「素読み」を行うのが基本です。
「素読み」については次の項で解説します。この項では初校と再校の「赤字合わせ」について述べます。
再校校正は、「初校」と「再校」を左右に見やすく並べて行うことになります(右手で赤字を入れるならば、左側に初校を右側に再校を置くことになります)。
初校に入れた修正を見ながら(指で追いながら)、再校が正しく修正されているか確認し、もし正しく修正されていない(あるいは修正がもれている)場合にはその箇所に赤字で訂正内容を記入します。
修正の要領は基本的に初校校正の場合と同じです。ただし、再校校正では修正が少なくなり製作担当者が見落としてしまう可能性があります。このため再校校正では修正箇所をが目立つように大きめに丸囲みをする習慣があります。

初校で確認した箇所には必ずチェックをいれる。あわせて、赤字合わせは一度ではなく最低2回行う。
どんな人でも見落としはあります。これを避けるためにも「確認箇所へのチェック」と「最低2回の赤字合わせ」を心がけてください。
初校の赤字の箇所だけでなく、その前後・周辺も確認する。
赤字合わせの途中で疑問点がでたらマーキングして付箋を付けておく。
赤字合わせの途中で初校にはなかった誤りに気がつくごとがあります。明らかな誤りの場合には修正してかまいませんが、誤りかどうか判断に困る場合があります(例:用語の統一)。このような場合にはその場で判断せず後から見直す意味のマーキング(たとえば鉛筆で丸囲みする)を行いあわせて付箋を付けておきます。
これは、赤字合わせの途中にほかの作業を入れると集中力が途切れ誤りをおかしやすいばかりか、途中で問題を解決しようとすると時間効率が悪いためです。疑問点などは素読みで見つかったほかの問題点とともに一括して解決するほうが効率的です。
赤字合わせをしている途中でほかの用事をしなければならないことがあります(たとえば電話をとる)。このようなときにはどこまで赤字合わせをしたかを忘れないように確認した最後の箇所に後で消せるマーキングを入れる習慣を付けてください。
赤字が入った校正(例:初校)とそれを修正した校正(例:再校)の赤字合わせが完了したら、確認し終わった校正の最初に(済)と明記してきます。たとえば、初校の最初に(済)と明記し「初校については完全に作業が終わった」ことを示しておきます。
これで初校については完全に手が離れたことになりますが、製作がすべて完了するまで初校を廃棄してはいけません。
![]()
テクニカルライティングセミナー
マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント
Copyright:Takaaki-YAMANOUCHI/2002-2010
山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所
Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute,Ltd.
![]() takaaki@yamanouchi-yri.com
takaaki@yamanouchi-yri.com